ICHIGO 二都物語 六田登
これは面白かった。特に前半の引き込まれ具合が半端無い。
六田登というと「F」や「ダッシュ勝平」のイメージが強いが、これも名作だと思う。前半に限れば。
梅川一期という連続殺人犯の生涯を描いた物語。
1952年大阪。戦後の復興の中で産声を上げた主人公梅川一期。生後まもなく患った肺炎のため片方の肺を摘出することとなる。その大きな手術痕に対する劣等感が彼の人格形成に大きな影を落としていく。

世界と自分との距離をうまく掴めず常に後ろめたさを感じていた一期は、小学六年生の時に体験した友人の死をきっかけに狂気を帯びていくこととなる。
昭和27年から64年(平成元年)までが舞台となり、戦後の昭和史をなぞった形で物語は進んでいく。作者の六田登も同じ27年生まれであるため、時代の空気感が良く出ているように思う。特に幼少時から「就職」するまでの丁寧な経済成長期の描写がなんとも味わい深い。
漫画としては「就職」以降のテンションが落ち気味なのが否めない。それまでは「どこにでもいそうな少年」の繊細な心理描写が物語の原動力であったように思えるが、以降は狂人の破滅を見届ける視点へとシフトしていったように感じる。登場人物もそのほとんどが異常さを増していき、リアリティが喪失されていく。狂気は伝染していくという意味合いの描写なのだろうか。終盤はまるで人間味のなくなった一期が死に場所を探し続けるように堕ちていく。その最期は何ともやるせない。
というお話。全10巻という長さも良い塩梅だと思う。絶版本だから全巻そろえるの結構大変だと思うが。特に後半は古本屋でも見かけない。最近はkindle版で読むことが出来る(1巻無料)。表紙絵のタッチが本編のものと違うのが気に入らないが(扉絵からの引用)。
以下ネタばれ含む考察
さて、物語は戦後の混乱が落ち着きだした昭和27年に始まり、昭和天皇が崩御した64年に終わるわけだが、これにはどういった意味があるのだろうか。記事タイトルに「連続殺人犯の昭和史」と使ったが、これはコンビニ版の煽りに倣ったものである。作中にはところどころで当時の世相を反映した描写が挟まるが、本編とはあまり関係がない。強いて言えばファッションぐらいだろうか。一期が家出した後の同棲生活や、久保登場時の政治思想などは当時色が強いが、時代の流れという強い力の作用によって物語が展開されたわけではない。
「文系は作者の気持ちでも考えてろよ」と言われそうではあるが、この作品において作者がテーマとして掲げたものについて史実と本編とを照らし合わせて考えてみる。
一期の生まれた昭和27年はサンフランシスコ講和条約によって日本の主権が回復した年である。つまり戦後日本の生まれた年だと言える。その後すぐに一期は肺炎になり片方の肺を摘出する。以降、それがコンプレックスとなり12歳のあの日を迎える。一期が抱えていた劣等感の源は「自分の不完全さ」であろう。付き纏う後ろめたさが自分の存在価値を曖昧にしていた。
これは、日本が獲得した主権はアメリカから与えられたものだという鬱屈したコンプレックスに重なるのではないか。当時の国民感情がどうであったかは定かではないが、サンフランシスコ講和条約について調べれば、賠償責任などの項目において「寛大な処置」という印象を受ける。つまりはアメリカを筆頭とした連合国により「与えられた」独立といったものだ。
昭和39年、アジアで初めてのオリンピックが開かれる。これにより日本は世界に対してはじめて対等の立場であることを自負出来た。世界と自分との距離が定まったのである。同年、12歳の一期は文也を殺め、自我を確立する。作中のテレビ放送では開幕式の様子が流され「開会、宣言です」の言葉通り、この事件を
きっかけとして一期の人生が動き始める。
昭和44年、高校生になった一期はボブディランに傾倒し、自分の価値観の正しさを確かめるためにヒッチハイク先の村で殺人を犯す。この時点では衝動的な行動と見える描写だが、後に岩井との対話で確信的であったと述べている。
戦後25年を経過し、日本は飛躍的に成長して大国となりつつあった。その中でこれまで水面下の存在であった政治闘争や公害といった負の側面が
噴出し、国の在り方について多くの場面で議論された時代であった。つまりは再度その自我の妥当性を問われたわけである。これは翌年開催された
高度成長のシンボルとしての大阪万博の成功によってその多くを不問に付した。日本の方向性は正しかったとされたのである。同年、安田講堂陥落によって学生運動は終焉を迎え、過激さを増す政治闘争は民衆の支持を得られず先鋭化していき、一部の人間のものとなっていった。
一期は岩井の下で暴力団員となり、その殺人衝動を社会化することにより自我の証明を行う。
昭和48年、20年以上右肩上がりだった経済成長に陰りが見え始める。第一次オイルショックである。暴力団のヒットマンとして順風満帆であった一期だが、岩
井の意思を汲んだつもりで行った柳木の残党狩りが裏目に出て、帰る場所をなくした一期は以降放浪の身となる。その中で岩井に対する小さな疑念や殺人中毒症
状ともいえる不可解な体の反応など、後年一期の精神を蝕むものが萌芽する。
作中のモノローグ「以後、時代は内向する。」と同調するように一期は異常さを増していく。
昭和63年、バブル景気の真っただ中である。その名の通り泡沫の様な実態の無い狂乱の時代、一期は初九という夢から覚めて、自分の人生に蹴りをつけるため日本へと帰る。バブルの時代に敢えて自分の現実を見定めるのである。一方、弟の利行は自分の造るアメニティシティに実感が持てない。知り合った綾も同様に生活に実態感がないと漏らす。この二人は時代の象徴であり、一期と対照的な存在として描かれる。
一期は自分が快適に暮らせる都を作ると残し、岩井を殺害。その時、岡は綾を失った利行に対して「都市づくりに犠牲はつきもの」と言い放つ。一期と利行。二人は互いに犠牲を払い都を作るのである。
一期は自身が一番実感のある方法で、利行は実感の無いままに。

一期により完成間近であったアメニティシティのモニュメントが破壊される。それは空が反射する鏡面状の外壁が表すように、実態感の無い空虚さの象徴を、現実的なダイナマイトを用いて強い意志で粉砕したのである。これを以て実態の無い何かは現実によって破壊され、後には何も残らなかった。
この時昭和が終わり、翌年バブル経済は破綻するのである。
連載開始が1990年(平成二年)であるため、バブル経済の解釈など、現在とは異なる捉え方があるかもしれないが、作者は史実を軸にその影の部分をシニカルに取らえ、梅川一期という人格を与えたのではないだろうか。つまりは戦後昭和という時代の一つの側面を擬人化したものであり、昭和が終わった時に失われた何かを描こうとしていたのだと思われる。それは鬱屈から来る歪んだ正しさであったり、成熟することを求められた社会であったり、不安感であったり、緊張感
だったのではないかと本作を読んで感じた。
本作が全体を通して名作となりえなかったのは、中盤以降の地に足の付いていないような浮ついた展開によるところが大きい。
一期が人格を形成していく過程での、文也殺害に至る緊張感が全てであり、殺人が非日常の刺激から日常的なものへと変化した時点で物語は終わっているのである。
単行本全10巻が2冊の合本として出ています。
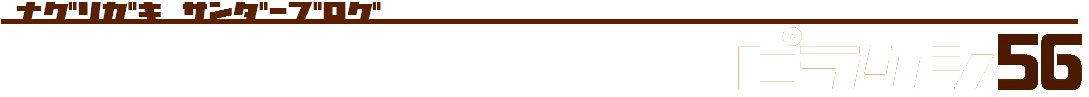




































理由は、千便万科に付けられるけれど内戦戦争以外で殺人はならんよデスノート殺人教室しかり何故こうした話が流行るのか其は末法末世だからに他成らず心に健やかな健全さが無いからだろう